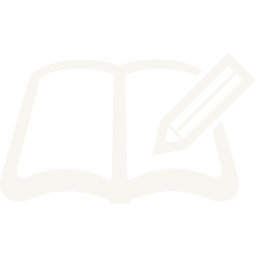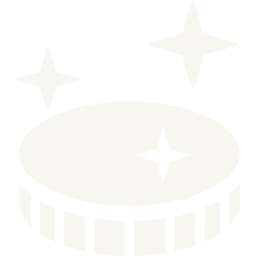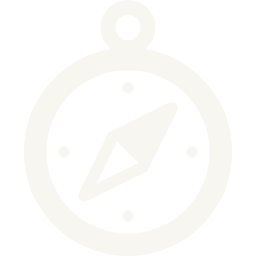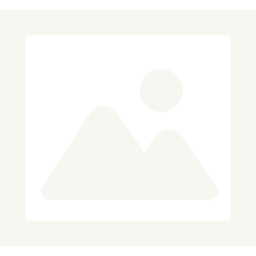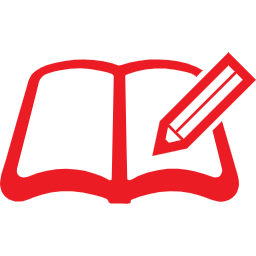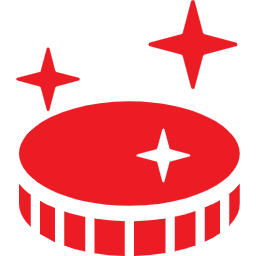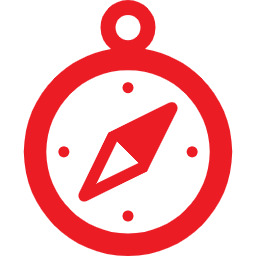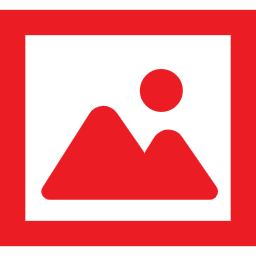「食」のメディア
秋にとれる刀みたいな魚だから秋刀魚って言うと思っていませんか?
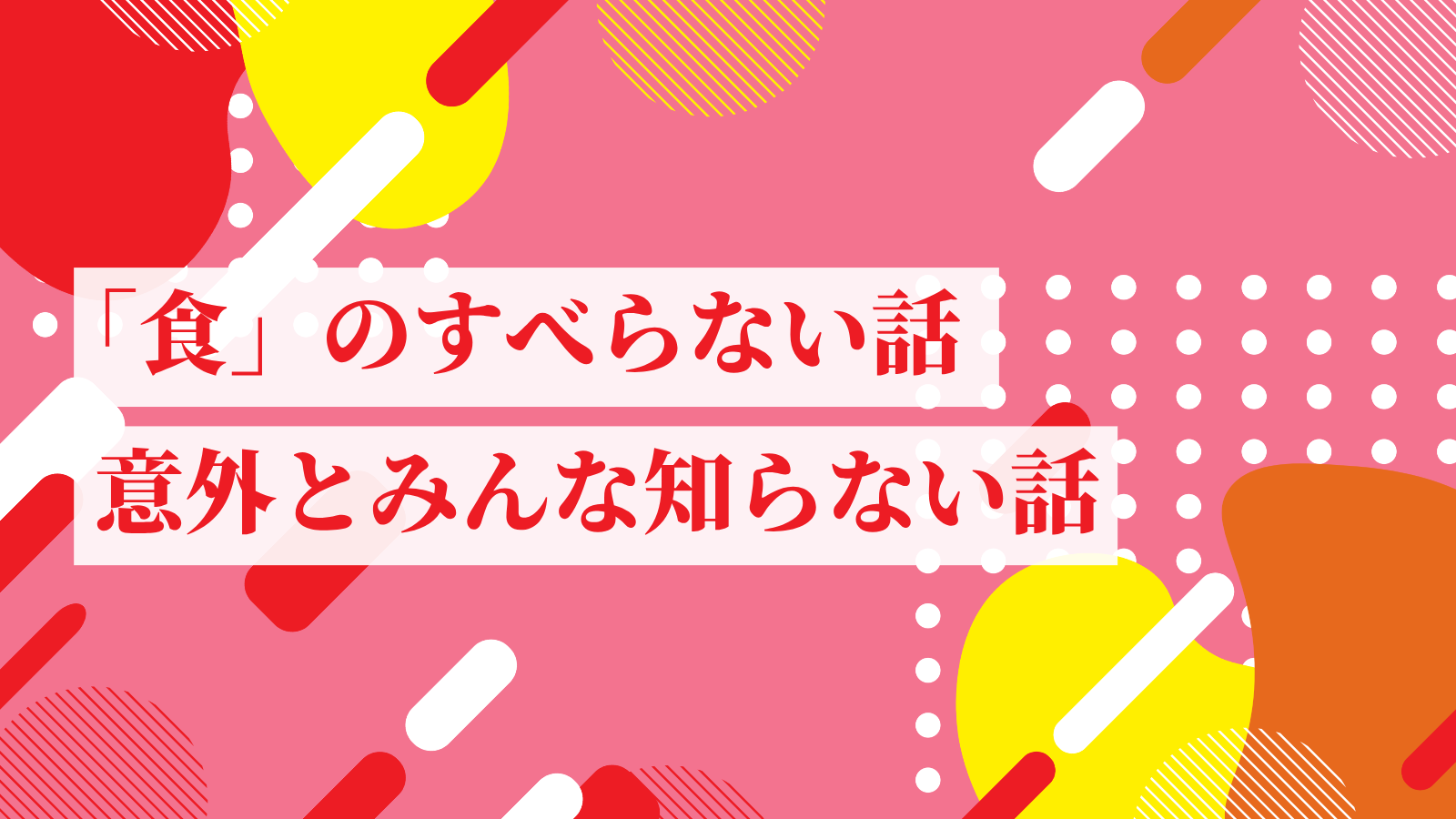
高級魚になりつつあるサンマ
私が子どもの頃は、1匹80円ぐらいでスーパーに発泡スチロールの箱にドカッと入れられて販売されていました。
最近では、そんな販売をしているスーパーを見なくなりましたね。
近年漁獲高の減少で、高級魚になりつつあるサンマですが、そんなサンマについて深堀りしていこうと思います。
みなさん、サンマと言えば「秋刀魚」という字をイメージされると思いますが、明らかに当て字であることはみなさんも承知の上だと思います。
昔に流行った「夜露死苦」みたいな当て字ならまだしも、サンマ=秋刀魚は、音すら合っていない。
普通に読めば、「しゅとうぎょ」ですからね・・・
ちなみに、サンマは一文字で「鰶」と書くこともできます。
一般的には「コノシロ」と呼ぶことが多く、この漢字をご存知の方は、コノシロの方が馴染み深いとは思います。
鰶の所以は、江戸時代にサンマが水揚げされると、みんながお祭り騒ぎのように喜んだというところから、この字が使われたと言われています。
話は戻りまして、なぜサンマが秋刀魚なのか?
みなさんもお察しの通りですが、「秋に取れる刀の様な魚」というところから来ていると言われています。
元々、秋刀魚は「狭真魚(さまな)」や「沢魚(さわま・さわんま)」と呼ばれていました。
狭真魚(さまな)は、細長い魚という意味で、太刀魚なども該当します。
奇しくも、秋刀魚と太刀魚は今やは一文字違うだけの魚なので、当時は同類として扱っていたのかもしれませんね。
ただ、秋刀魚はダツ目、太刀魚はスズキ目なので、種としては全然違う種類に分類されています。
沢魚(さわま・さわんま)は、群れをなして泳ぐ魚という意味で、こちらの漢字が使われていたという説もあります。
この秋刀魚という漢字が使われだしたのは、大正の頃で「秋刀魚の歌」という詩が広がり、今やサンマは秋刀魚という字を当てる事が一般的になりました。
まだ100年ぐらいの歴史しかない言葉としては比較的最近の言葉だと言えます。
ここで皆さんに一度思い返してほしいんですが、サンマを食べる時どうしていますか?
私は、塩を振って焼いて食べます。
その時、内臓はどうしていますか?
俗に言うワタですね。
取り出していますか?
だいたい、取り出すことなくそのまま焼いて食べていると思いますが、これには理由があるんです。
サンマやイワシなどは「無胃魚」と呼ばれ、読んで字の如く、胃がない魚です。
胃がないということは、食べたものが体に溜まりにくい
すなわち、腐りにくい(鮮度が落ちにくい)
なので、サンマなどの無胃魚は、ワタを取らずに食べることができます。
サンマのワタは、ビタミンAやミネラルが豊富で栄養価に富んでいるので、積極的に摂取したいところですが、同時にプリン体も豊富なので取り過ぎると痛風の原因になるので注意しましょう
いかがでしたか?
私は子供の頃から、秋刀魚をどう読んだらサンマになるのが不思議で仕方なかったのですが、理屈じゃないんですよね!
ちなみに、サンマはダツ目というお話をしましたが、ダツ目にはサヨリやトビウオなどが分類されていますが、その中にメダカも含まれています。
まさかの、サンマとメダカは親戚になるんですよ!!
記事の感想をクリックしてストーンをゲット!
他の記事も見る
GET