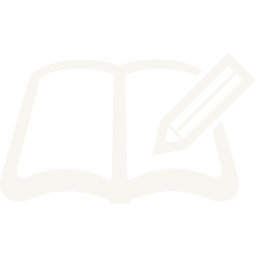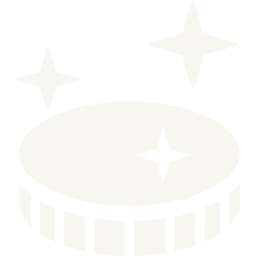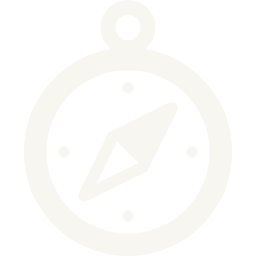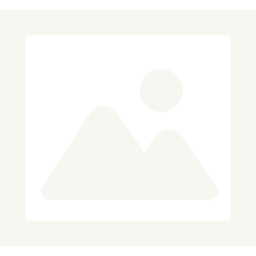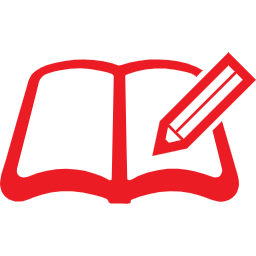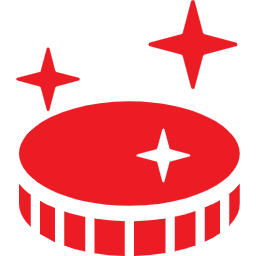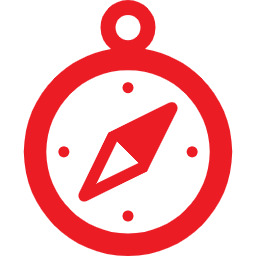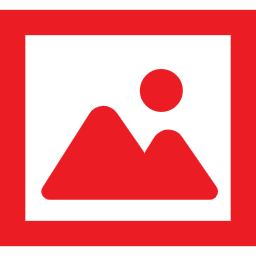「食」のメディア
納豆は腐っているって言うけど・・・
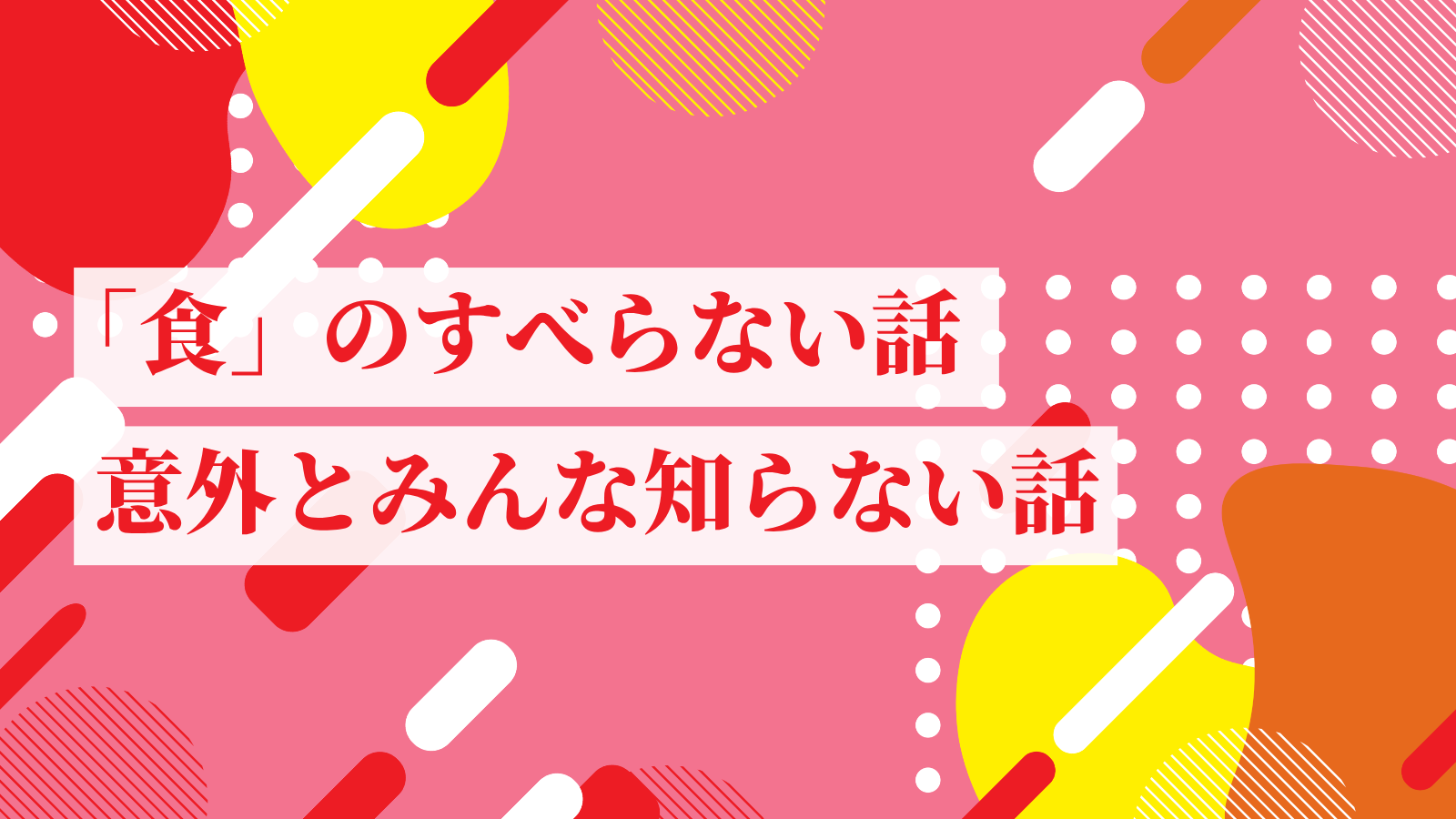
今回は、ユーザー様よりいただいた内容で深堀りしていきたいと思います。
みなさん、納豆は好きですか?
私は子供の頃「あんたは納豆食べさせていたら静かになるからね」と言われてたぐらい納豆が好きだったようです。
中学校の給食の時間に納豆が出た時、食べれない子が隣のクラスから私のところに納豆を持ってくるぐらい納豆好きが有名で、私の記憶に残る限りでは、机の上に納豆が15パック積み重ねられてたので、今思えば異常な光景ですね・・・。
先生もさすがに止めろよ。とか思いますね。
とは言え、納豆は好き嫌いがはっきり分かれる食べ物で、大人になった今では、周りに気を使いながら食べてますが、みなさんはどうでしょうか?
この納豆ですが、諸説はあるものの歴史は古く弥生時代にさかのぼります。
稲作が大陸から伝来した頃のお話です。
この頃に既に煮豆を食べる風習があった弥生人は、稲刈りの後に残るワラを寝床などに使っていました。
このワラと煮豆が出会った事が納豆の始まりではないかと言われています。
納豆が出来るには、納豆菌という細菌の活動が必要ですが、弥生時代の住居の環境が納豆菌には活動しやすい環境にあった事、住居内にあったワラがあった事、煮豆を食べていた事。
この3つが揃い、偶然にも納豆菌が住居内で繁殖し、煮豆を作る過程で付着し納豆が生まれたと言われています。
もう一つ有力な説としては、源頼朝の先祖が起源ではないかと言うお話です。
納豆の歴史を調べると「八幡太郎義家」という名前が必ずと言っていいほど出てきます。
この人は、別名「源義家」で、玄孫が源頼朝になります。
この人が、馬の餌用の煮豆を俵に入れて運んでいると、その煮豆が糸を引いてしまい、恐る恐る試食したら美味しかったから、兵士の食料にしたというお話があります。
これが2つ目の説です。
これは個人的な感想ですが、どっちの説も「なんか、不衛生・・・」
1つ目の説も、2つ目の説も「結局腐っとるやないかい」と。
ここで疑問です
腐っているのに、なぜ今日まで食べられ続けているのか?
そして、なぜ食中毒にならなかったのか?
これは「腐る」と「発酵」の根本的な違いがあることです。
納豆や味噌、チーズをはじめとする発酵食品
「腐敗」も「発酵」も微生物や細菌の活動により起きる現象という点では同じですが、人間の管理下にあれば「発酵」、なければ「腐敗」です。
そして、微生物の種類が異なるという点もあります。
納豆は、納豆菌
味噌は、乳酸菌・麹菌・酵母菌など
チーズは、乳酸菌やカビをはじめとする「スターター」と呼ばれる微生物
腐敗は、サルモネラ菌・カンピロバクター・黄色ブドウ球菌・・・などの微生物です。
(厳密には乳酸菌なども腐敗の原因にもなりうるのですが、今回は割愛します。)
細菌や微生物が根本的に異なり、人間の管理下にある納豆は腐っているのでは無く発酵と言います。
もちろん、納豆も適切な管理をしなければ、腐敗の原因になる細菌は付着しますが、他の食材に比べ、すでに納豆菌が発酵という活動をしているので、腐敗させる細菌たちが付着しても活動を阻害する効果があります。
そのため、味噌やチーズなどの発酵食品は長期保存が可能なわけですね。
人間にとって良い働きをする細菌たちのおかげで、悪さをする細菌たちをやっつけてくれていたという事です。
ちなみに、人間の体内、外には常在菌などの微生物が常に活動していますが、その微生物の総重量は2kgにもなるそうです。
これは余談ですが、馬やゴリラなどの草食動物が、なぜ肉を食べずにあれだけの筋肉があるのか?
これも微生物の活動のおかげで、草食動物は体内の微生物の活動のために草を食べ、その微生物が生み出すタンパク質などを栄養分にすることで、筋肉を維持しているそうです。
いかがでしたか?
野菜を食べてマッチョになれるゴリラが羨ましいですね。
発酵、細菌の活動は奥深いので、またの機会に深堀りしたいと思います。
記事の感想をクリックしてストーンをゲット!
他の記事も見る
GET