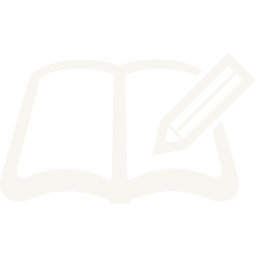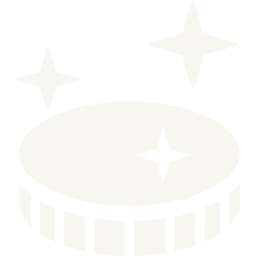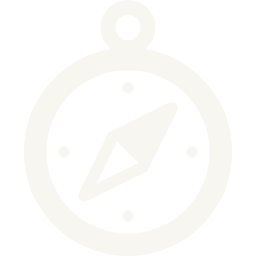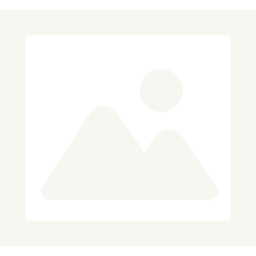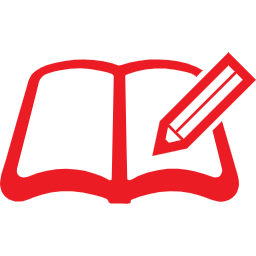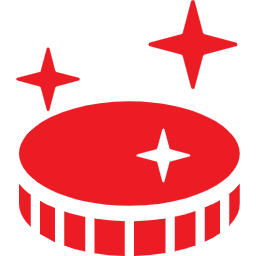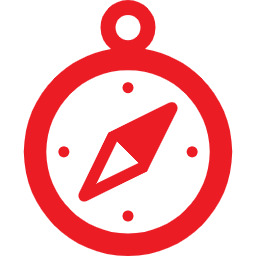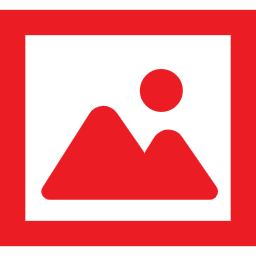「食」のメディア
3種類のソーセージに都市の名前がついている理由
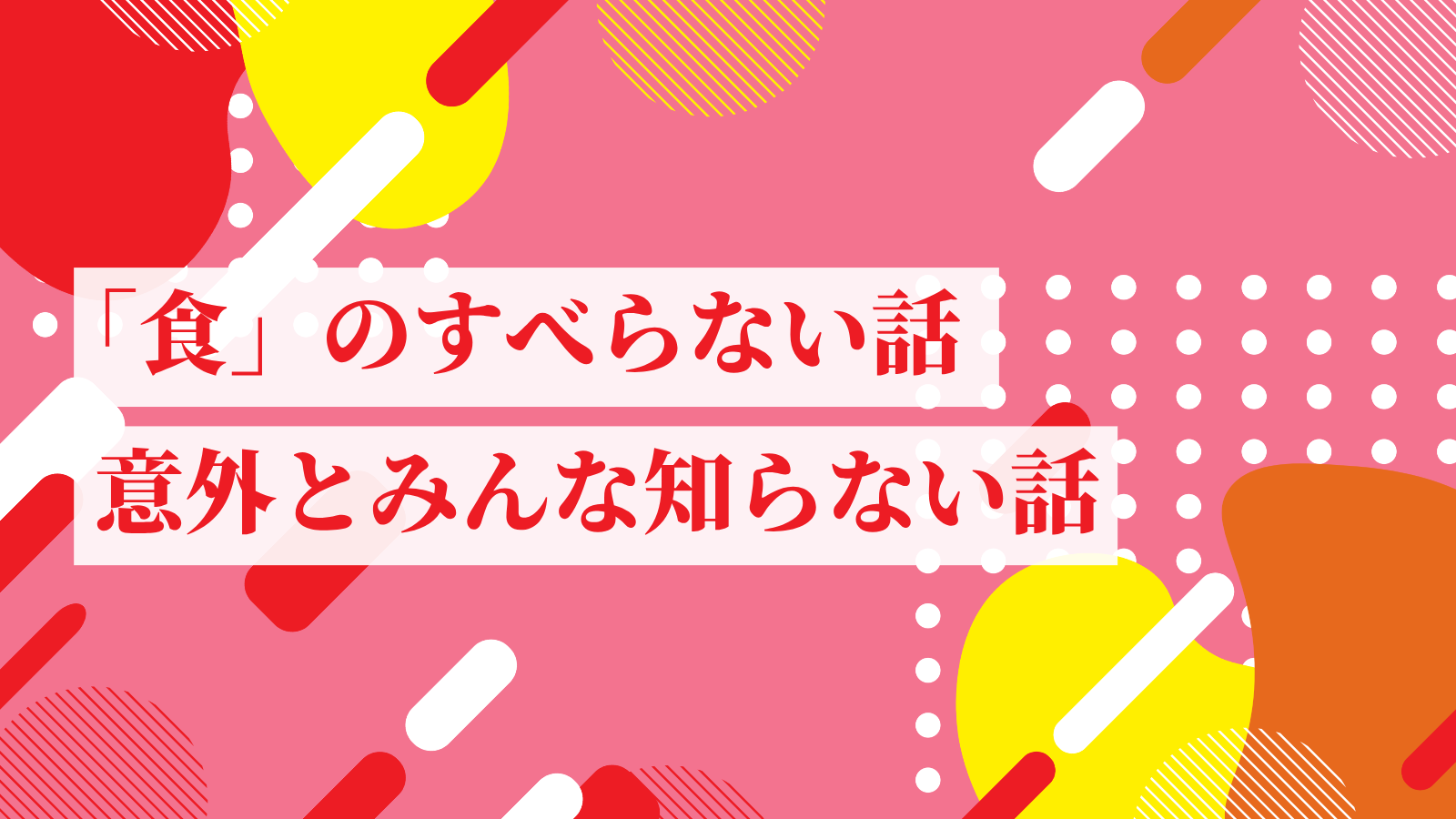
以前、ソーセージの違いについてアップさせていただきました。
あわせてこちらもご覧ください。
ソーセージとウインナーの違い言えますか?
⇒https://syokutsu.adpentas.com/trivia?trivia_id=0001RX0TMM
ウインナーは、オーストリアのウィーンから、フランクフルトはドイツのフランクフルトから、ボロニアは、イタリアのボローニャ地方から名付けられたと解説させていただきました。
では、なぜソーセージの名前にはヨーロッパの都市の名前がつけられているのでしょうか?
答えは簡単で、その都市で生まれたからそのまま都市の名前がつけられて、一般的な名称として普及しています。
今回は、もう少し掘り下げて解説していこうと思います。
語源や歴史的背景を学ぶことで、食への理解、その食自体が持っているポテンシャルや味の奥ゆかしさなどを感じていただければと思います。
まず、大元のソーセージについてです。
ソーセージは歴史が長く、紀元前にさかのぼるため正確な語源はわかりませんが、ラテン語の塩漬けを意味するSalsusから来ているのではないか、という説が一番有力であるとされています。
ちなみに、ソーセージは英語でもソーセージです。
ドイツ語で「ヴルスト」、フランス語では「ソシス」と呼びます。
ソーセージの発祥はエジプトあたりではないかとされており、その調理方法がドイツに伝わり、ヨーロッパ全土に広がったとされています。
ソーセージは塩漬けという意味から、長期保存を目的とした料理です。
これが、ドイツの厳しい冬の季節にマッチしました。
ドイツの冬は厳しく家畜の餌がなくなり餓死することが頻発していました。
そのため、餓死する前に肉をさばき長期保存するソーセージという料理がちょうど良かったんですね。
では、ソーセージの3種類「ウインナー」「フランクフルト」「ボロニア」について解説していきます。
まずウインナーは、オーストリアのウィーンが発祥です。
ドイツから広まったソーセージがオーストリアのウィーンで改良されて、販売されました。
これをドイツ語で「ウィンナー・ヴルストヒェン(ウィーン風のソーセージ)」と呼ばれ、ウインナーとして定着しました。
もともと、このウインナーは、ドイツで修行をしたソーセージ職人がオーストリアに持ち帰り改良した事が発端とされています。
次に「フランクフルト」
こちらは、ドイツの都市ですね。
ドイツ語で「フランクフルター・ヴルストヒェン(フランクフルト風のソーセージ)」と呼ばれ、フランクフルトが定着しました。
諸説はありますが、ドイツの食文化として、夜は手の込んだ料理は食べないのが伝統的とされています。
もう少し噛み砕くと、火を使わず、後片付けも簡単な質素でシンプルな料理で終わらせることが多く、手の込んだ料理は昼食に取るそうです。
ソーセージは、燻製しておりそのままでも食べれるため、ドイツの食文化、風土に適した料理と言えます。
フランクフルトは、そんな食文化でそれなりの食べごたえを求めるドイツ人にとって程よい大きさであったとされています。
次に「ボロニア」
イタリア語で、モルタデッラと呼ばれ、ものによってはハムと酷似しており、加熱なしでそのまま薄切りにして食べれる点から見てもほぼハムです。
ただ、ウインナーやフランクフルトと異なり、ボロニアの歴史は浅く、約400年程度とされています。
ゆえ、日本では同列に扱われていますが、別の料理と考えて良いほど異なります。
ウインナーやフランクフルトは燻製で作るのに対して、ボロニアは加熱します。
また、オリーブやピスタチオなども混ぜ込む事を考えると全然違う料理であると言えます。
また、フランクフルトは長期保存する保存食として進化してきたのに対して、ボロニアは貴族向けの高級料理として進化してきた背景があります。
いかがでしたか?
身近なソーセージですが、歴史的背景を学んで行くと食のポテンシャルや食べ方などが見えてくると思います。
記事の感想をクリックしてストーンをゲット!
他の記事も見る
GET