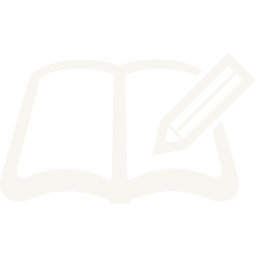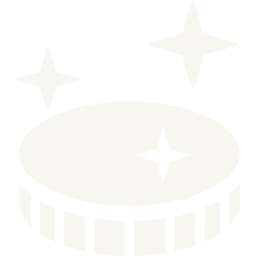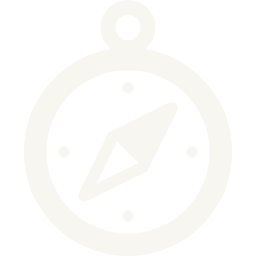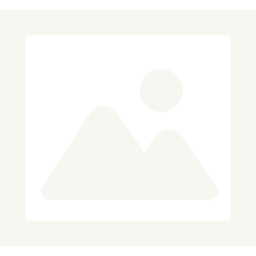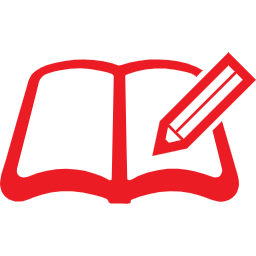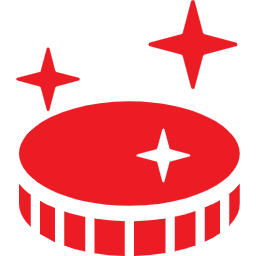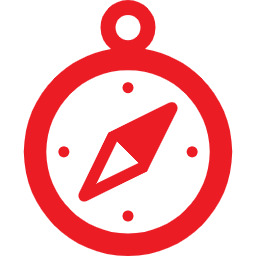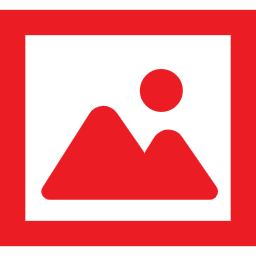「食」のメディア
お酒は百薬の長とよく言ったもんだ
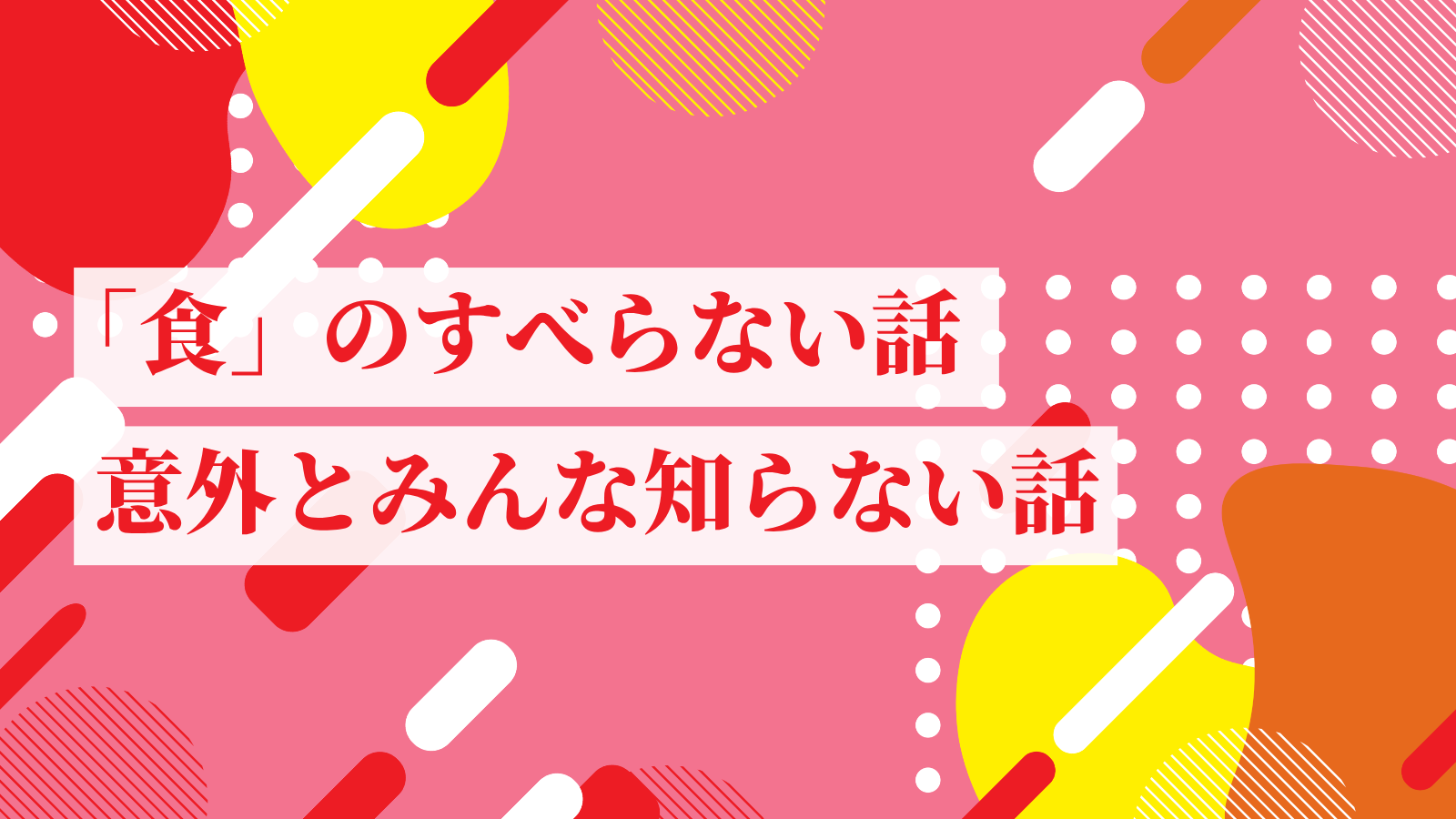
「お酒は百薬の長」という言葉をご存知でしょうか?
どんな薬よりも適量の酒が病に効くということわざですが、元々は中国の言葉です。
薬と表現しているのに、全く医学的知見がない状態で生まれた言葉なんですよね。
遡ること、2000年
その当時の中国の王である王莽は、「酒、塩、鉄」を国主導での専売制にしようとしました。
・塩は食肴の将 = 食には塩が一番大事
・酒は百薬の長 = 適度な酒は薬にもなり、お祝いの席でも嗜む
・鉄は田農の本 = 鉄器は農業の基本
という理由をつけて、だから国が主導して、安定供給するために専売にします。
という宣言の一節が今日に残るというわけです。
と言いつつ、これは表向き、これら3つは儲かる品として国が特権を握っておきたいという大人の事情がある訳で、理由なんぞなんでも良い。
国民が納得する理由を適当に作って、宣言しただけという・・・
それが未だに語り継がれているわけです。
ですが、今ではお酒扱いのある飲み物は、生まれた当時、本当に薬として発明されたお酒があるんですよ。
今回は、薬として発明されて、その発明が今の日本のチューハイを作ったと言っても過言ではないお酒を深掘りしていこうと思います。
さて、もったいぶってますが、薬として発明されたお酒の答えを先にお伝えしておきましょう。
それは、みなさんも一度は耳にしたことがある
「ジン」
です。
「あれれ?おかしいぞー?」
でおなじみのメガネに蝶ネクタイ、短パンにサスベンダーの坊やが主人公のアニメの敵に同じ名前のお兄さんがいますね。
そして、ウォッカ、ラム、テキーラ
このジン、ウォッカ、ラム、テキーラは世界4大スピリッツと呼ばれ、世界で愛されるスピリッツ(蒸留酒)です。
話は戻りまして、このジンは元々オランダ人の医師によって作られました。
当時、チフスやマラリアといった伝染病が蔓延する中で、利尿作用、解熱作用があることで知られていた「杜松(ねず)」の実から作らたジンを薬局で販売したことがジンの始まりとされています。
当初は、薬として販売していましたが、いつしか薬ではなくお酒としてオランダ国内で流行し、フランス語で杜松を意味する「ジュニエーブル」と呼ばれて親しまれていました。
これが、スイスのジュネーブと一緒にされて「ジェネバ」に変わり、イギリスで「ジン」と短縮されて今の呼び名「ジン」になりました。
このジンがイギリスで空前の大ブーム
原材料が安く手に入り、良質なお酒であったこと、当時のイギリスの国王がオランダの人であり、オランダ初のジンを優遇したことも相まって、広く浸透し世界に広まっていきました。
そして冒頭でも紹介した、ジンがチューハイを作ったという部分を解説したいと思います。
このジンがいつ日本にやってきたかは正確には分かっていませんが、少なくとも江戸時代にはあったとされ、長崎の出島にいた外国人が飲んでいたことは分かっているようです。
ただ、日本人が飲むようになったのは明治時代で、外国人居留地にあった商社がジンを輸入販売したのが、日本で広まった要因ではあるのではないかと言われています。
とは言え、今のような手軽なお酒ではなく、当初は高級嗜好品として扱われていました。
それが徐々に日本国内に浸透し、国内生産が成功して価格が下がり、今のように一般的に親しまれるようになりました。
この国内生産ができるようになったのは、ジンを作るのに必要な機械がイギリスで開発され、その機械が日本にやってきたことが始まりです。
ジンはスピリッツですが、スピリッツは原料をアルコール発酵させた上で、その抽出したアルコール分を蒸留して作られます。
蒸留しなければ、醸造酒と言い、日本酒やビール・ワインなどがこれに分類されます。
(粗く表現していますので、厳密には少し違うのですが・・・)
そして、この蒸留にも方法が大きく分けて2つあり、単式か連続式に分けることができます。
単式は、1〜2回の蒸留
連続式は、連続3回以上蒸留
に分けることができます。
蒸留酒の一種である焼酎で、単式の焼酎を「乙類」
連続式を「甲類」と区別しています。
プレミアム焼酎などは基本的に乙類であることが多く、蒸留は単式になります。
単式は、原料の味や香りが残るのが特徴で、連続式は純粋なアルコール分だけ残すため精製度は高いものの原料の味や香りはあまり残りません。
なので、プレミアム焼酎のような個性的で風味などを楽しむ焼酎が単式を採用する理由になります。
そして、このジンを作るためにイギリスで開発されたのが連続式蒸留の機械で、これが日本に伝わったおかげで、焼酎を連続式で作れるようになり、甲類が登場しました。
レモンチューハイなどのベースは焼酎甲類などが使われており、このジンがなければ、連続式蒸留の機械も開発されず、結果焼酎甲類が開発されず、レモンチューハイが生まれなかったかもしれませんね。
いかがでしたか?
嘘八百とまでは言いませんが、酒は百薬の長って元々大人の事情で生まれた言葉だったにも関わらず、2000年も経つ今でも語り継がれるって事は、人間の本能的な部分にフィットしたんでしょうね。
言わば「お酒を飲む大義名分」的な存在の言葉になったんでしょう。
ちなみに、焼酎甲類は複雑な機械を使う連続式蒸留で作られているのに、乙類に比べると安価なのは、先述した通り、原材料の味や香りが残りにくい製法なため原料の質はあまり問わない部分にあります。
乙類の様な原料の質が味の決めての様な焼酎ではないので、語弊を承知で言うと安い原料を使って作ってもそれなりの精度のお酒にできることが理由とされています。
これは、余談ですが、日本で流通する甲類の焼酎の原料の多くは麦、米、とうもろこしで、世界三大穀物と言われる大量に生産されている安価な原料が使われています。
記事の感想をクリックしてストーンをゲット!
他の記事も見る
GET