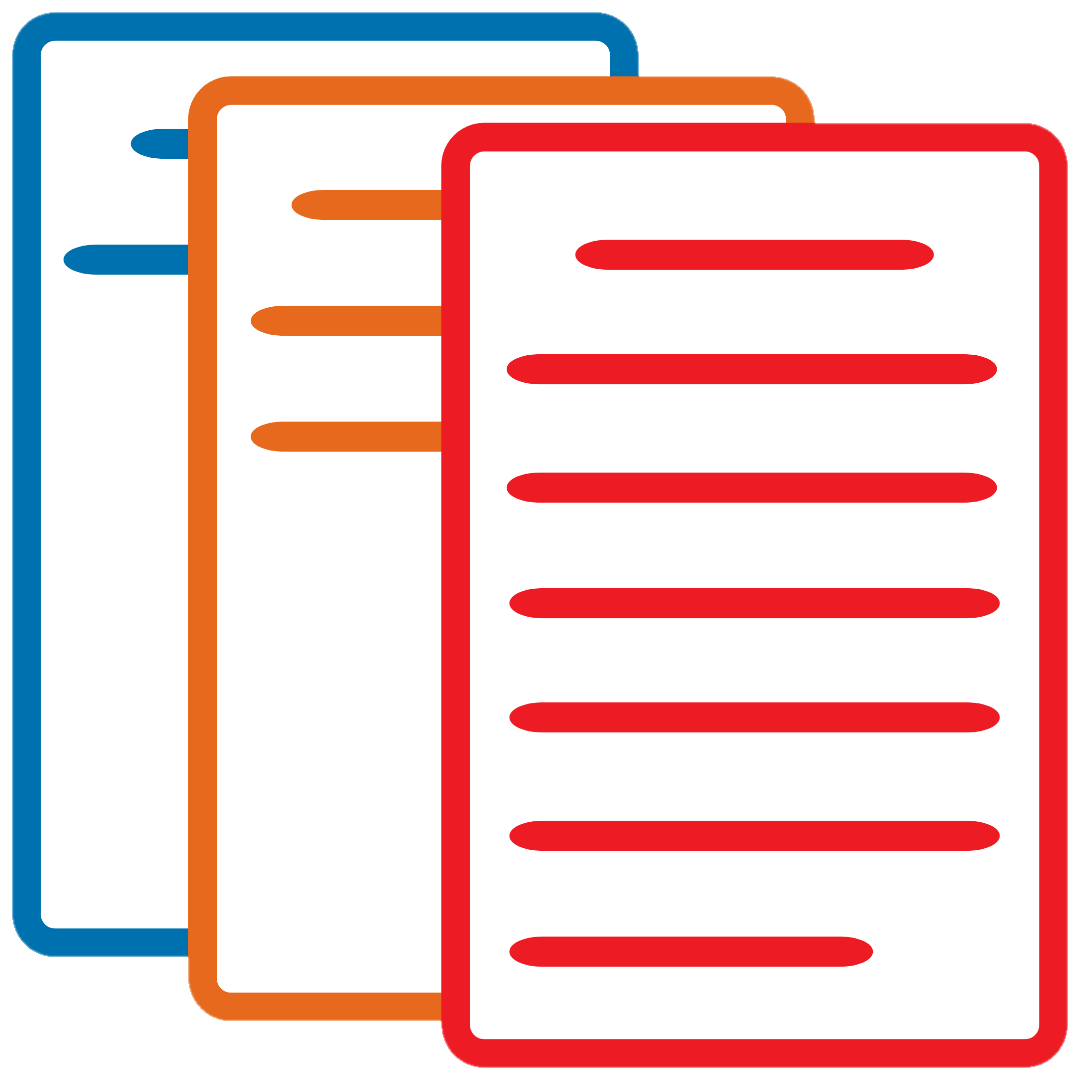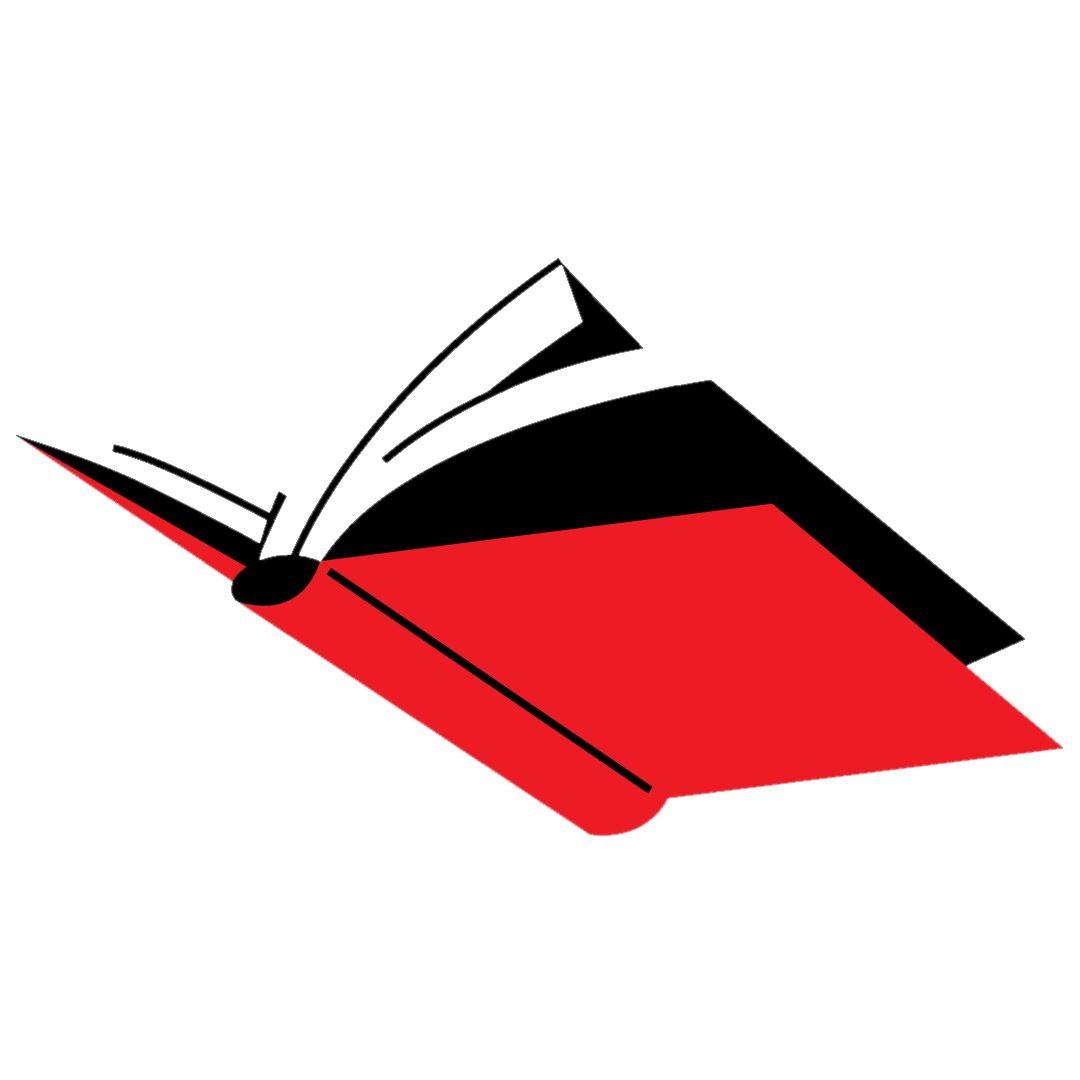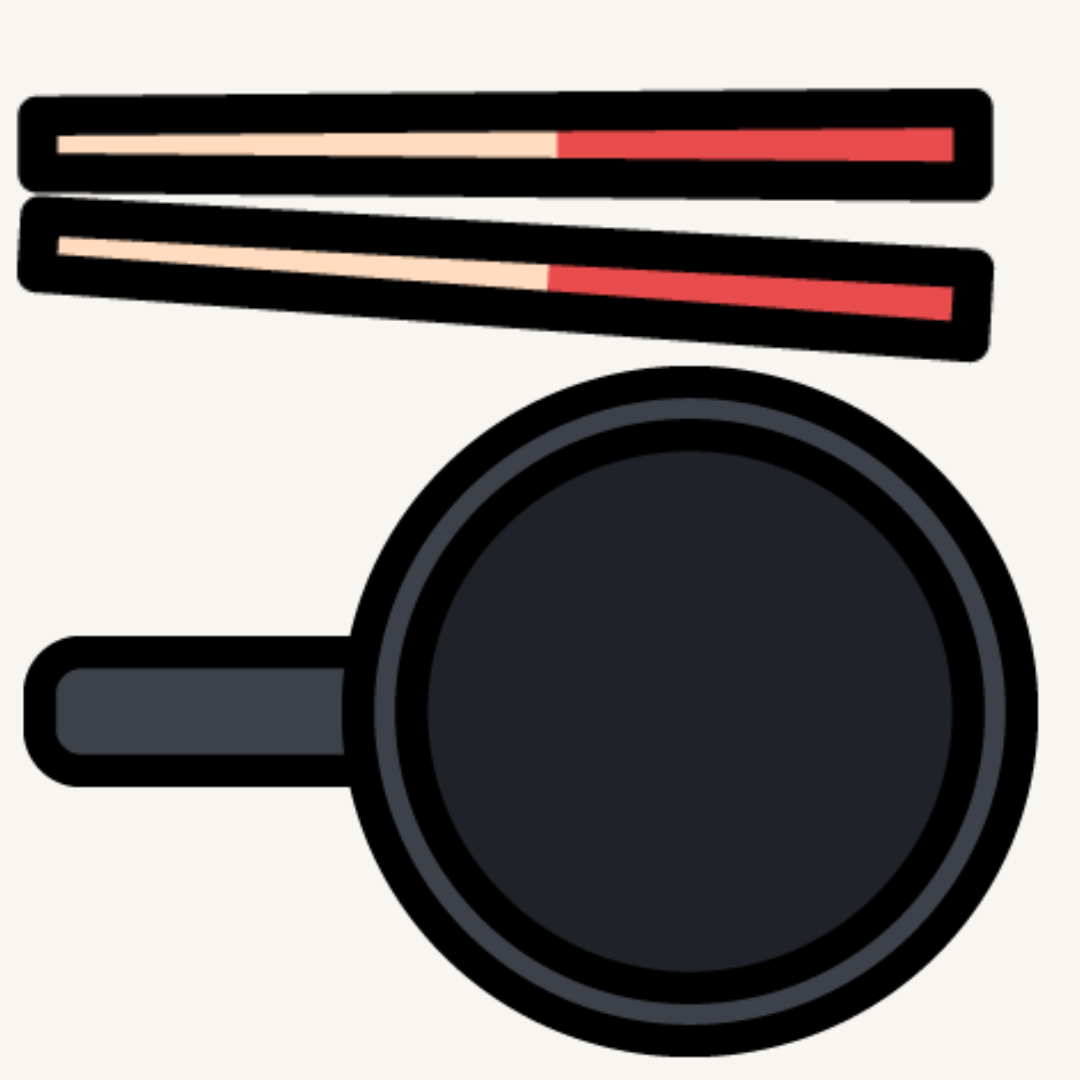今日の記念日:
カニカマの日ラブラブサンドの日ショートケーキの日カツカレーの日回転寿司記念日長野県りんごの日CREAM SWEETSの日「愛ひとつぶ」の日韓国キムチの日甘酒ヌーボーの日旬を迎えた食材:
ほうれん草水菜白菜大根カブにんじんかぼちゃさつまいもねぎカリフラワーブロッコリーキャベツケールレンコン春菊ごぼう長芋自然薯海老芋こんにゃく芋菊芋ラディッシュコールラビチンゲン菜パセリ落花生白ねぎトレビスクワイ高菜ウコン野沢菜さといもゆりねムカゴルッコラすだち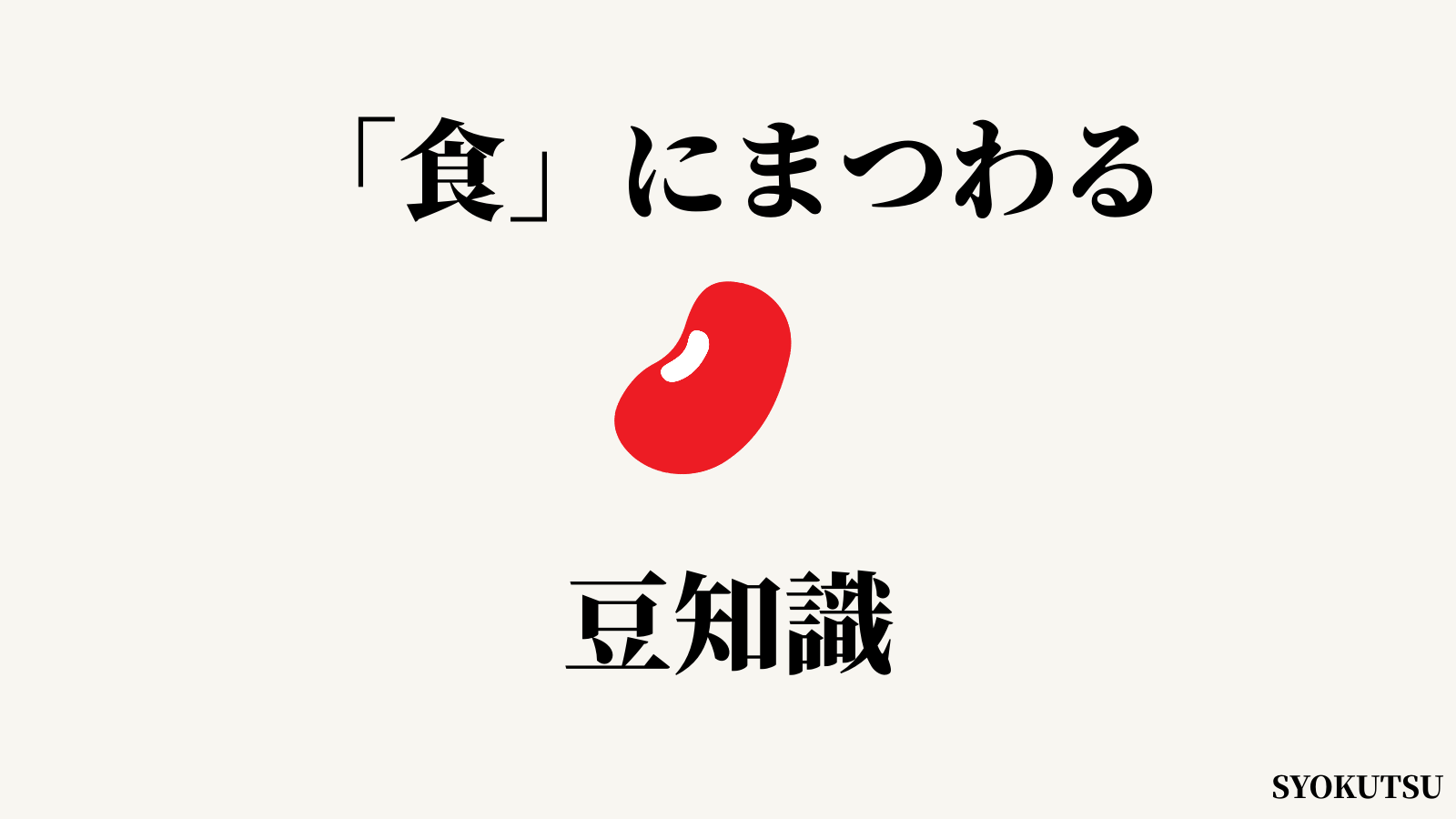
奥の深い缶詰
みなさんは、缶詰を使いますか?
ツナやコーン、サバや焼鳥
今では、たこ焼きの缶詰やヒグマの缶詰もあるそうです。
防災の観点からうちでは缶詰と水を常備しています。
缶詰で思い出した話なのですが、焼鳥屋で働いている頃
「油の一斗缶を開けといて」
とバイトスタッフにお願いしたことがあるのですが、その時
「これ、どうやって開けるんですか?」
という質問が返ってきたことを思い出しました。
今の世代は缶切りの存在、使い方を知らない人もいる事に衝撃を受けました。
よく考えると、最近の缶詰って缶切りを使わなくてもプルタブがついているので、使わないんだなぁ
と・・・。
今回はそんな缶詰について深掘りしていこうと思います。
さて、缶詰の歴史をさかのぼってみましょう。
缶詰ができた発端は、あの有名な皇帝「ナポレオン」だったということはご存知でしょうか?
まだ下級士官であったナポレオンは、遠征先での食料が粗末で粗悪であることに強い懸念感を抱いていました。
それもそのはずで、遠征先で食べれる食べ物は乾燥したパンか塩漬けや酢漬けしたものしかありませんでした。
味が不味いは百歩譲っても、そもそも腐っていて食べれない場合が多く、いつも飢えと戦い、そんな状況で士気が上がるわけもない。
と考えたナポレオンは政府に依頼を行い、政府は懸賞金とともに公募を行いました。
その時に名乗り出たのが菓子職人でした。
この菓子職人は、瓶に食材を詰め、軽くコルクで栓を行い、煮沸することで中の空気を抜いて栓をしっかりすると長期保存できることを発見しました。
これが、缶詰の始まりで、開発当時は瓶詰めだったということです。
この製造方法がヨーロッパ各地に広まり、のちにイギリスで缶詰が発明されて、瓶詰めから今の缶詰の原型ができました。
しかし、この缶詰をあける肝心の缶切りが世の中に無く、発明されたのは、缶詰の登場から50年後で、それまではノミとハンマーで開けていたそうです。
今考えると「缶詰開発したら、開ける道具も普通開発するでしょ?」と思いますよね?
でも、人類って昔からこんな中途半端な開発を多くしてきているんですよ。
これは余談ですが、例えば、水洗トイレとトイレットペーパー
水洗トイレの原型は紀元前2200年と言われており、トイレットペーパーが商品化されたのは19世紀
今では、あたり前の水洗トイレですが、それとセットになるはずのトイレットペーパーが開発されたのは、水洗トイレの登場からなんと4000年
それまでどうしてた?
どうしてたんでしょうね・・・。
話は逸れましたが、日本に缶詰が伝わったのは1870年頃と言われており、はじめての缶詰はイワシの油漬けだったそうです。
そして、その頃から缶詰の形は円柱形だったそうなんですが、なぜ缶詰は円柱形だと思いますか?
考えてみてください。
輸送するとき、トラックで運びます。
トラックの荷台は四角です。
そうなると、缶詰を入れた段ボールは四角の方が多く入り、安定しますね。
でも、丸い缶詰を四角段ボールに詰めると、絶対にデッドスペースが生まれます。
輸送の観点から見れば缶詰は四角の方が絶対に効率が良いはずです。
今では四角の缶詰もありますが、多くは丸です。
これは、製造時のコストに関係しているそうです。
詳しい計算などは省きますが、表面積が同じであれば、円柱形が1番中身を詰めることが可能で、製造時の効率が円柱形が一番いい形だそうなんです。
だから、輸送面から見た時のデッドスペースを考慮しても、円柱形を採用している理由だそうです。
いかがでしょうか?
ちなみに日本で製造されている缶詰で1番高価な缶詰は1個
17,000円
タラバガニの脚肉詰めだそうです。
それならカニ食べに行くわ・・・。
でも、このカニ缶は40年続くロングセラー商品だそうです。
気になる方は、マルハニチロの公式通販サイトのみで販売しています。
これは余談ですが、缶詰は平均的に3年程度で賞味期限を迎えます。
が、中身は完全な無菌状態になっており、腐敗する原因の微生物が無の状態です。
理論上、未開封であればかなりの期間(10年ぐらい行けると言う方もいます)保存が可能です。
(ただし、理論上の話で、賞味期限が切れた缶詰を食べる際は自己責任でお願いします)
この記事はいかがですか?
記事を評価してストーンをGET
ゲスト さま
現在見られているページ 02:15更新
Warning: Undefined variable $common_parts_ver in /home/r6599674/public_html/syokutsu.adpentas.com/common/common_top_set_mobile.php on line 8
閲覧履歴
運営情報
©2025 SYOKUTSU
POWERED BY ADPENTS
お知らせ
Warning: Undefined variable $common_parts_ver in /home/r6599674/public_html/syokutsu.adpentas.com/common/common_top_set_mobile.php on line 9
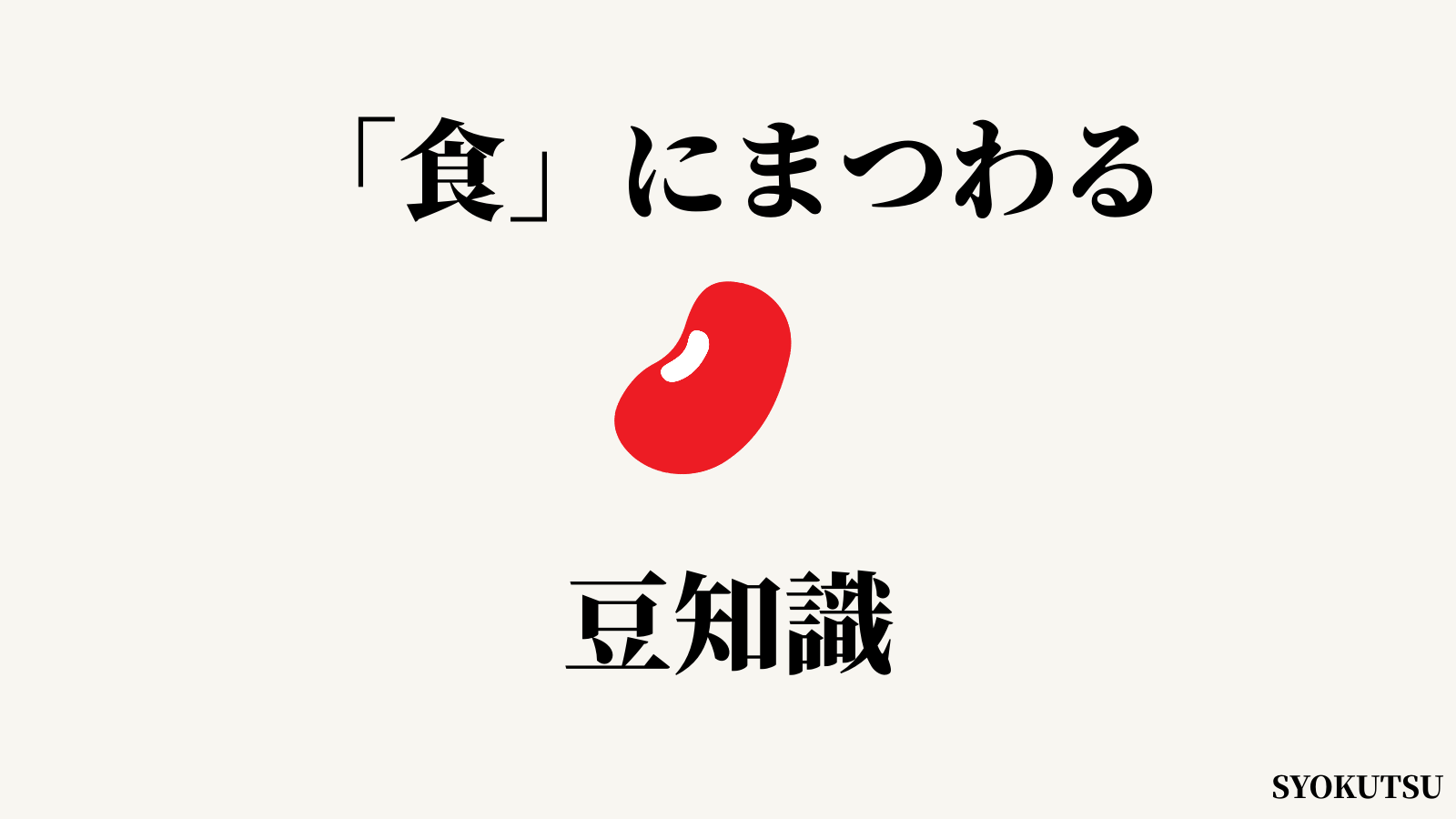
奥の深い缶詰
みなさんは、缶詰を使いますか?
ツナやコーン、サバや焼鳥
今では、たこ焼きの缶詰やヒグマの缶詰もあるそうです。
防災の観点からうちでは缶詰と水を常備しています。
缶詰で思い出した話なのですが、焼鳥屋で働いている頃
「油の一斗缶を開けといて」
とバイトスタッフにお願いしたことがあるのですが、その時
「これ、どうやって開けるんですか?」
という質問が返ってきたことを思い出しました。
今の世代は缶切りの存在、使い方を知らない人もいる事に衝撃を受けました。
よく考えると、最近の缶詰って缶切りを使わなくてもプルタブがついているので、使わないんだなぁ
と・・・。
今回はそんな缶詰について深掘りしていこうと思います。
さて、缶詰の歴史をさかのぼってみましょう。
缶詰ができた発端は、あの有名な皇帝「ナポレオン」だったということはご存知でしょうか?
まだ下級士官であったナポレオンは、遠征先での食料が粗末で粗悪であることに強い懸念感を抱いていました。
それもそのはずで、遠征先で食べれる食べ物は乾燥したパンか塩漬けや酢漬けしたものしかありませんでした。
味が不味いは百歩譲っても、そもそも腐っていて食べれない場合が多く、いつも飢えと戦い、そんな状況で士気が上がるわけもない。
と考えたナポレオンは政府に依頼を行い、政府は懸賞金とともに公募を行いました。
その時に名乗り出たのが菓子職人でした。
この菓子職人は、瓶に食材を詰め、軽くコルクで栓を行い、煮沸することで中の空気を抜いて栓をしっかりすると長期保存できることを発見しました。
これが、缶詰の始まりで、開発当時は瓶詰めだったということです。
この製造方法がヨーロッパ各地に広まり、のちにイギリスで缶詰が発明されて、瓶詰めから今の缶詰の原型ができました。
しかし、この缶詰をあける肝心の缶切りが世の中に無く、発明されたのは、缶詰の登場から50年後で、それまではノミとハンマーで開けていたそうです。
今考えると「缶詰開発したら、開ける道具も普通開発するでしょ?」と思いますよね?
でも、人類って昔からこんな中途半端な開発を多くしてきているんですよ。
これは余談ですが、例えば、水洗トイレとトイレットペーパー
水洗トイレの原型は紀元前2200年と言われており、トイレットペーパーが商品化されたのは19世紀
今では、あたり前の水洗トイレですが、それとセットになるはずのトイレットペーパーが開発されたのは、水洗トイレの登場からなんと4000年
それまでどうしてた?
どうしてたんでしょうね・・・。
話は逸れましたが、日本に缶詰が伝わったのは1870年頃と言われており、はじめての缶詰はイワシの油漬けだったそうです。
そして、その頃から缶詰の形は円柱形だったそうなんですが、なぜ缶詰は円柱形だと思いますか?
考えてみてください。
輸送するとき、トラックで運びます。
トラックの荷台は四角です。
そうなると、缶詰を入れた段ボールは四角の方が多く入り、安定しますね。
でも、丸い缶詰を四角段ボールに詰めると、絶対にデッドスペースが生まれます。
輸送の観点から見れば缶詰は四角の方が絶対に効率が良いはずです。
今では四角の缶詰もありますが、多くは丸です。
これは、製造時のコストに関係しているそうです。
詳しい計算などは省きますが、表面積が同じであれば、円柱形が1番中身を詰めることが可能で、製造時の効率が円柱形が一番いい形だそうなんです。
だから、輸送面から見た時のデッドスペースを考慮しても、円柱形を採用している理由だそうです。
いかがでしょうか?
ちなみに日本で製造されている缶詰で1番高価な缶詰は1個
17,000円
タラバガニの脚肉詰めだそうです。
それならカニ食べに行くわ・・・。
でも、このカニ缶は40年続くロングセラー商品だそうです。
気になる方は、マルハニチロの公式通販サイトのみで販売しています。
これは余談ですが、缶詰は平均的に3年程度で賞味期限を迎えます。
が、中身は完全な無菌状態になっており、腐敗する原因の微生物が無の状態です。
理論上、未開封であればかなりの期間(10年ぐらい行けると言う方もいます)保存が可能です。
(ただし、理論上の話で、賞味期限が切れた缶詰を食べる際は自己責任でお願いします)
この記事はいかがですか?
記事を評価してストーンをGET

.png)