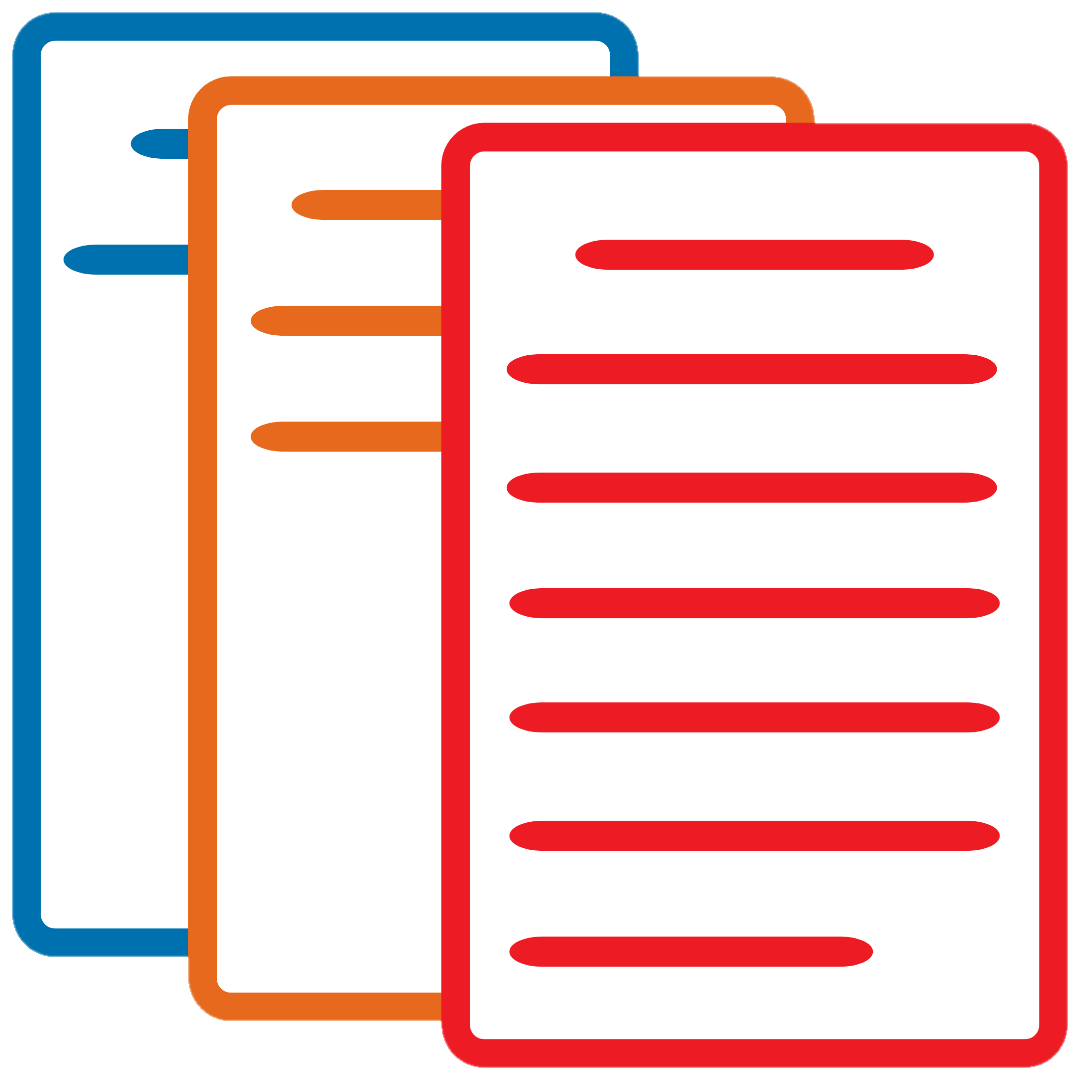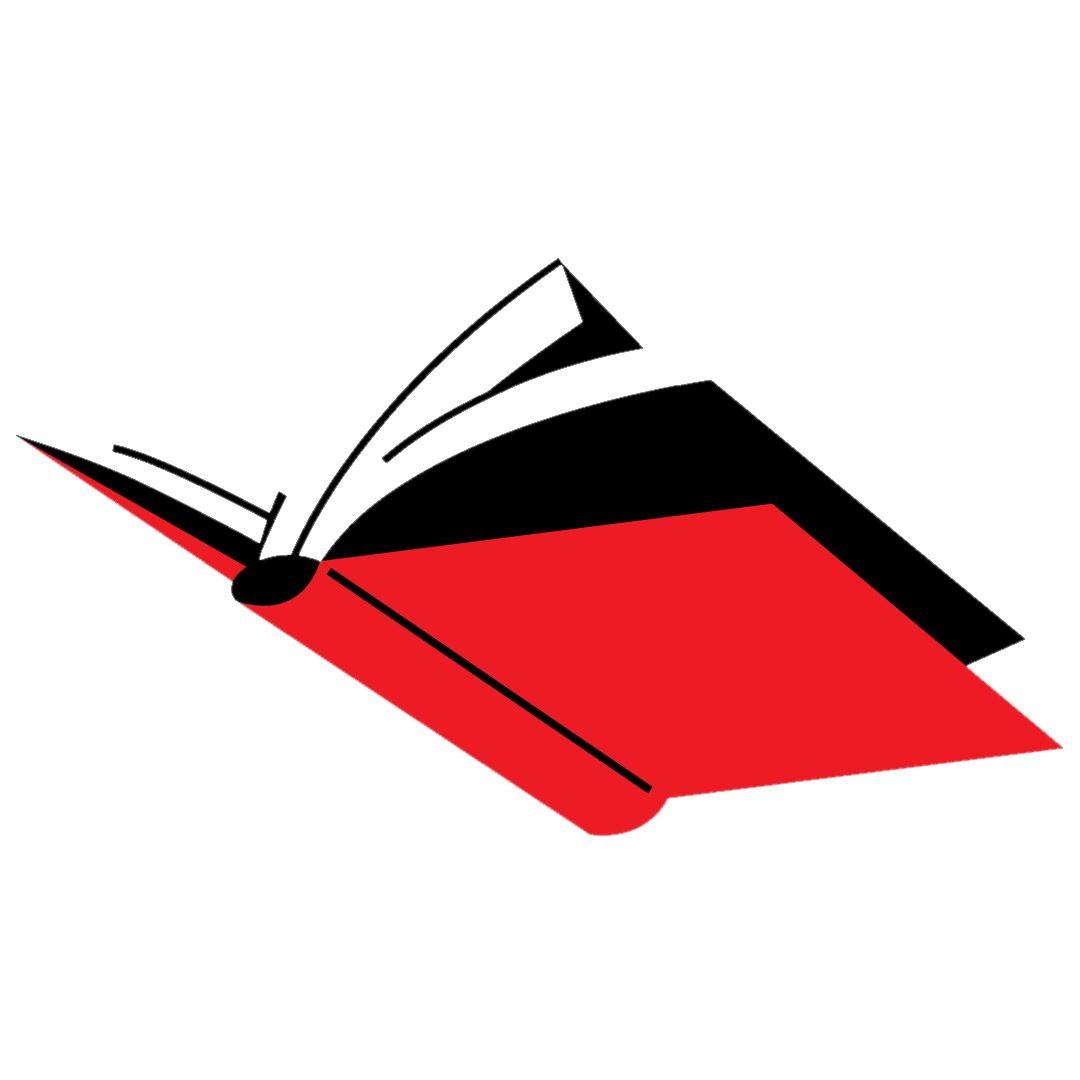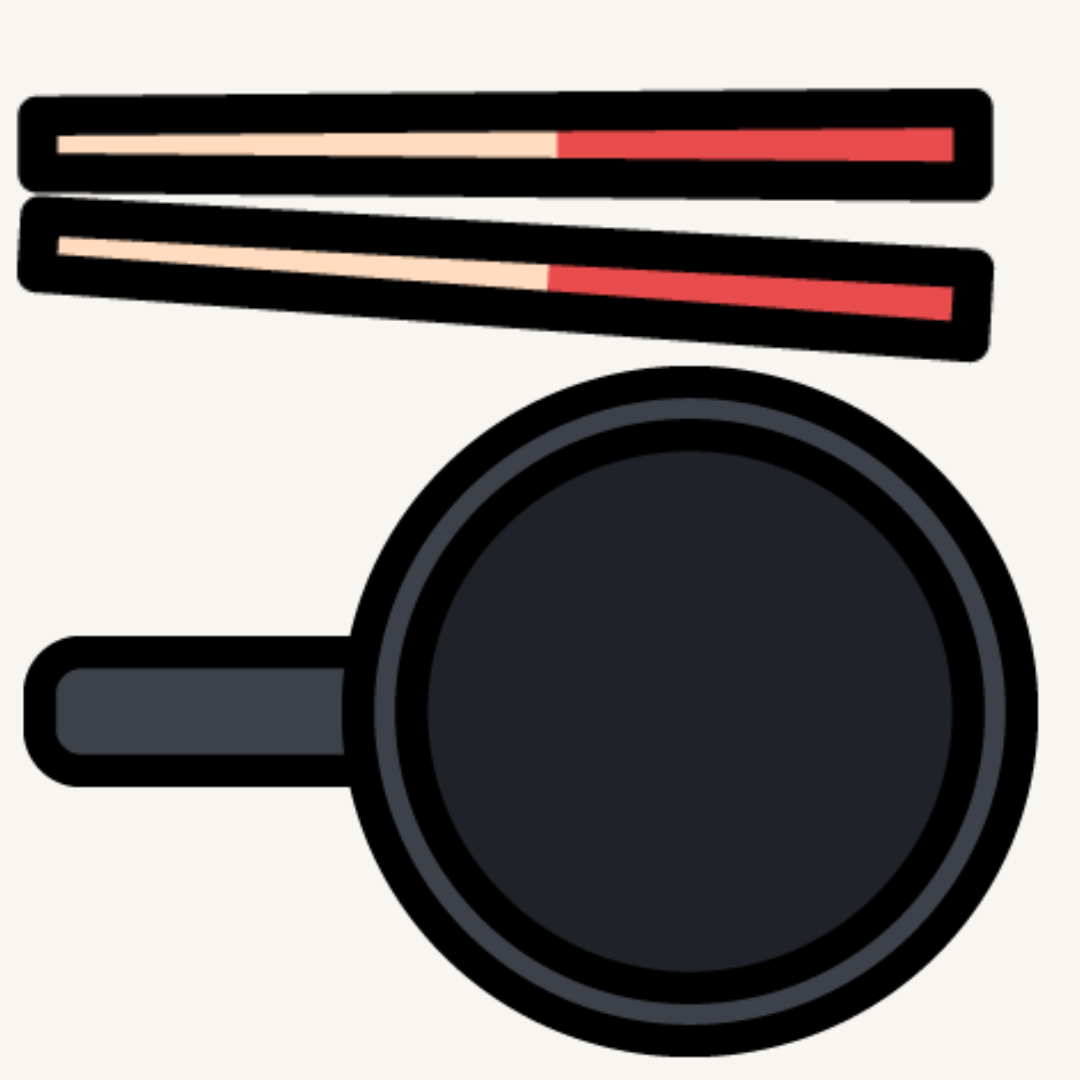今日の記念日:
カニカマの日ラブラブサンドの日ショートケーキの日カツカレーの日回転寿司記念日長野県りんごの日CREAM SWEETSの日「愛ひとつぶ」の日韓国キムチの日甘酒ヌーボーの日旬を迎えた食材:
ほうれん草水菜白菜大根カブにんじんかぼちゃさつまいもねぎカリフラワーブロッコリーキャベツケールレンコン春菊ごぼう長芋自然薯海老芋こんにゃく芋菊芋ラディッシュコールラビチンゲン菜パセリ落花生白ねぎトレビスクワイ高菜ウコン野沢菜さといもゆりねムカゴルッコラすだち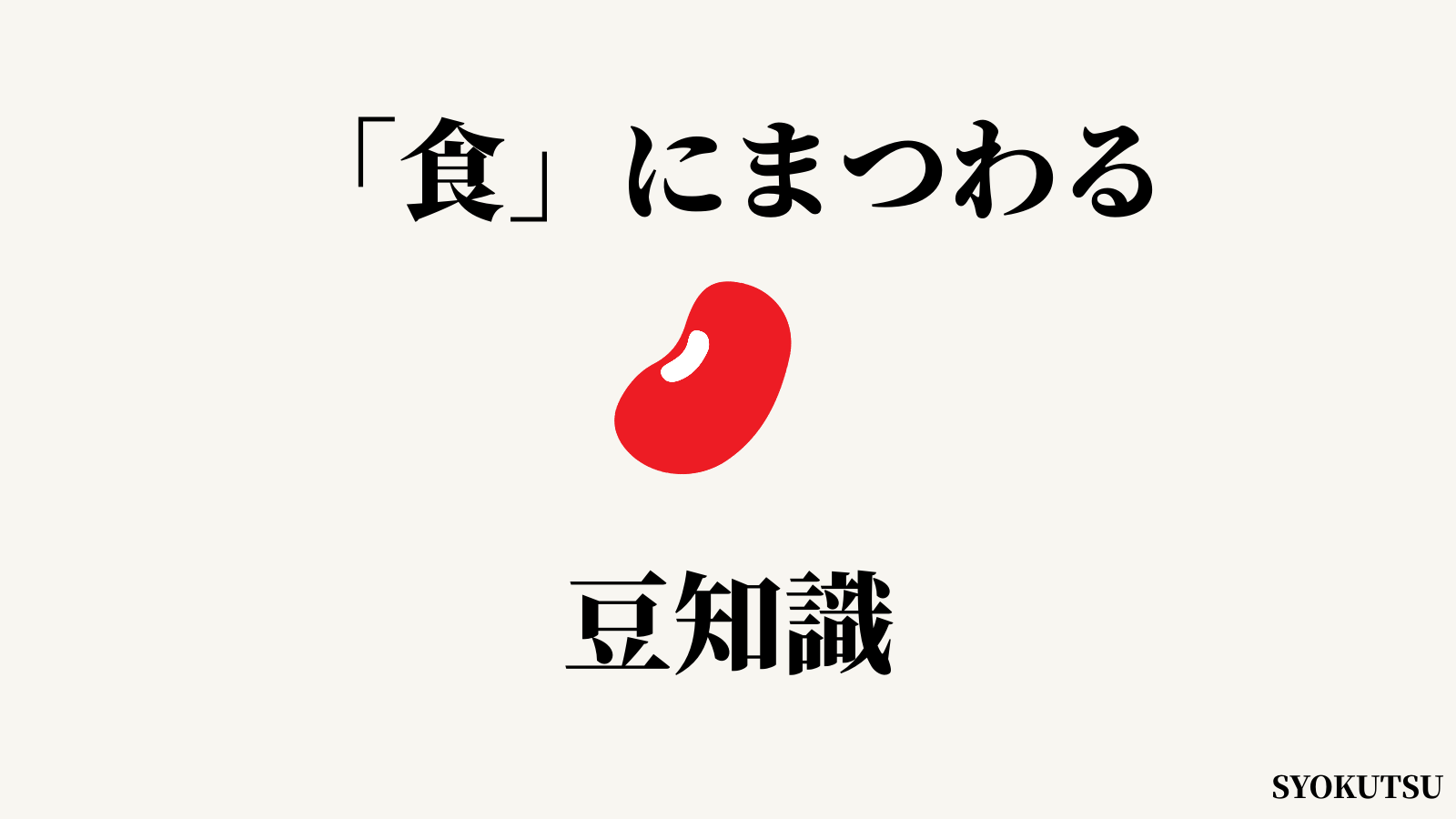
最後にお漬物を食べたのはいつですか?
みなさん、最後にお漬物を食べたのはいつですか?
この題材に決定して、ふと考えたのですが、考えてみると...
あれ?いつだっけ?となりました。
みなさんはどうですか?
牛丼チェーンでの紅生姜や博多ラーメン屋での無料サービスの高菜とかですか?
おにぎりの梅干し。梅干しも立派なお漬物ですからね!
梅干しの方が多いのかな?と勝手に推測していますが、最近では、コンビニのお弁当にお漬物がついていない場合もあり、意外にもお漬物を口にすることが減った気がしませんか?
実は、昔に比べお漬物の消費量は40%減というデータがあるぐらい、お漬物は肌感覚ではなく消費量が減っています。
そんな日本食のバイプレイヤーでもあるお漬物について今回は深堀りしていこうと思います。
さて、みなさん日本にはお漬物は何種類ぐらいあると思いますか?
代表的なところでいくと「たくあん」「梅干し」あたりですよね?
大区分でいくと、ざっと10種類です。
「塩漬け」
「醤油漬け」
「味噌漬け」
「かす漬け」
「麹漬け」
「酢漬け」
「ぬか漬け」
「からし漬け」
「もろみ漬け」
「その他(しば漬け等)」
これを細分化していくと、いろいろ枝分かれしていきますが、大きく分けるとこの10種類に集約されます。
この漬物の歴史は長く古くは2000年前に塩漬け文化がはじまり、平安時代に入ると酢漬けや粕漬けが始まりました。
この漬物文化は、ひっそりと続き、江戸時代に大きく発展しました。
ただの保存方法に過ぎなかった漬物は、江戸時代に味を楽しむことに重きをおかれるようになり、今のようなバリエーションに富んだ漬物文化になりました。
先述した通り、漬物は元々、食材の保存が目的でした。
保存とは、食材の腐敗を防ぐことです。
この腐敗という現象は、細菌の活動によって引き起こされる自然現象ですが、言い換えれば細菌が活動できないようにすれば、腐敗は起きない。と言えます。
細菌の活動条件は5つ
「水分」
「栄養分」
「温度」
この3つが揃うと、腐敗の原因の細菌の活動が活発になります。
栄養分を抜いてしまうと、せっかくの食材のメリットがなくなり、冷蔵庫がない時代に温度を一定に保つのは難しい。
となると「水分」を抜くしかなくなります。
そこで昔の人は、水分を抜くために塩に食材を漬けました。
これが漬物のはじりまりです。
これが副次的に細菌が生きていけない高濃度な塩分が実現されたことで、ダブルで腐敗を防ぐことができ、長期保存の手法として確立していきました。
しかし、最近では健康志向の高まりにより、塩分を気にする消費者にあわせて、塩分濃度の低い漬物が流通するようになりました。
この塩分濃度というところがポイントで、低すぎる塩分では食材の腐敗を防ぐ事ができないんです。
塩漬けで言うと、最低でも20%ぐらいの塩分濃度が必要と言われています。
この塩分濃度が20%以下で作られたお漬物は、お漬物なのに食材が腐敗することが起きて、2年前食品衛生法の改定により、お漬物を作る場合、保健所への届け出が必要になりました。
その様な背景もあり、近年の漬物離れが起きていると言われています。
そんな漬物ですが、日本ではじめて漬けられた食材はなんだと思いますか?
一応、記録として残っているものに限定しています。
大根?
きゅうり?
白菜?
正解は
瓜
だそうです。
瓜として記録されているので、きゅうりかもしれませんし、冬瓜かもしれません。
はたまたカボチャかもしれませんね!
カボチャはないか・・・。
個人の感想ですが、スイカの漬物は意外に美味しいですよ!
さて、いかがでしたか?
そういえば、最近漬物食べていないなと思った方、家でも余った野菜などに多めの塩を振って揉み込むだけで浅漬
味噌にみりんを入れて、その中に野菜を入れた味噌漬け
意外にも簡単に家でも漬物はできますので、一度お試しあれ!
これは余談ですが...
漬物の代名詞でもある「たくあん」
たくあんは、天日干しした大根を塩と麹で漬けた「麹漬け」に分類されるお漬物です。
云わば「大根の麹漬け」ですが、たくあんがたくあんと言われるのは、このたくあんを考えたのが「沢庵和尚(たくあんおしょう)」と言われており、この和尚様が作ったお漬物を徳川幕府三代将軍徳川家光が大変気に入り、「大根の麹漬け」の和尚様の名前から「たくあん」と名付けたと言われています。
この記事はいかがですか?
記事を評価してストーンをGET
他の記事
ゲスト さま
現在見られているページ 01:07更新
Warning: Undefined variable $common_parts_ver in /home/r6599674/public_html/syokutsu.adpentas.com/common/common_top_set_mobile.php on line 8
閲覧履歴
運営情報
©2025 SYOKUTSU
POWERED BY ADPENTS
お知らせ
Warning: Undefined variable $common_parts_ver in /home/r6599674/public_html/syokutsu.adpentas.com/common/common_top_set_mobile.php on line 9
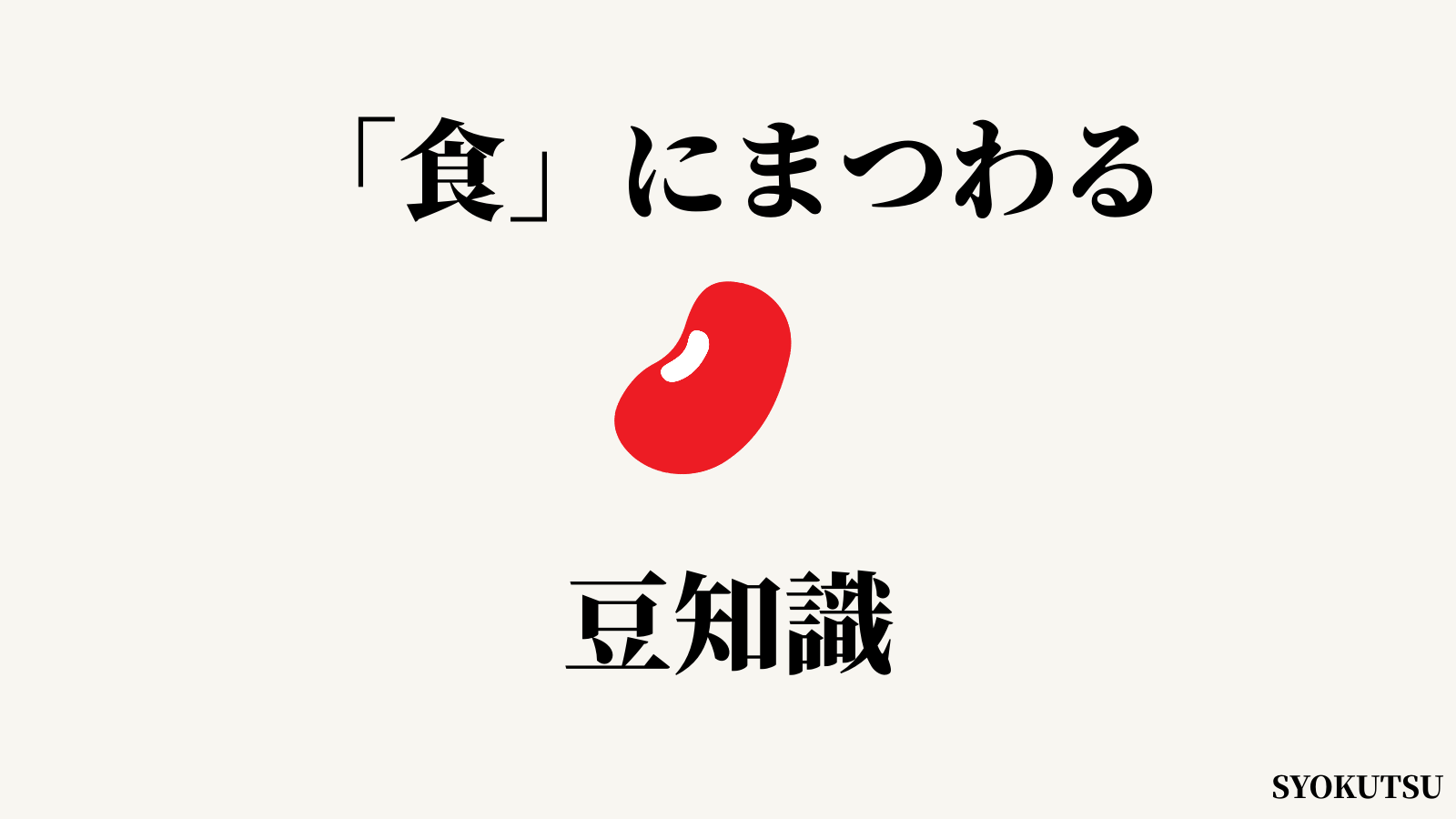
最後にお漬物を食べたのはいつですか?
みなさん、最後にお漬物を食べたのはいつですか?
この題材に決定して、ふと考えたのですが、考えてみると...
あれ?いつだっけ?となりました。
みなさんはどうですか?
牛丼チェーンでの紅生姜や博多ラーメン屋での無料サービスの高菜とかですか?
おにぎりの梅干し。梅干しも立派なお漬物ですからね!
梅干しの方が多いのかな?と勝手に推測していますが、最近では、コンビニのお弁当にお漬物がついていない場合もあり、意外にもお漬物を口にすることが減った気がしませんか?
実は、昔に比べお漬物の消費量は40%減というデータがあるぐらい、お漬物は肌感覚ではなく消費量が減っています。
そんな日本食のバイプレイヤーでもあるお漬物について今回は深堀りしていこうと思います。
さて、みなさん日本にはお漬物は何種類ぐらいあると思いますか?
代表的なところでいくと「たくあん」「梅干し」あたりですよね?
大区分でいくと、ざっと10種類です。
「塩漬け」
「醤油漬け」
「味噌漬け」
「かす漬け」
「麹漬け」
「酢漬け」
「ぬか漬け」
「からし漬け」
「もろみ漬け」
「その他(しば漬け等)」
これを細分化していくと、いろいろ枝分かれしていきますが、大きく分けるとこの10種類に集約されます。
この漬物の歴史は長く古くは2000年前に塩漬け文化がはじまり、平安時代に入ると酢漬けや粕漬けが始まりました。
この漬物文化は、ひっそりと続き、江戸時代に大きく発展しました。
ただの保存方法に過ぎなかった漬物は、江戸時代に味を楽しむことに重きをおかれるようになり、今のようなバリエーションに富んだ漬物文化になりました。
先述した通り、漬物は元々、食材の保存が目的でした。
保存とは、食材の腐敗を防ぐことです。
この腐敗という現象は、細菌の活動によって引き起こされる自然現象ですが、言い換えれば細菌が活動できないようにすれば、腐敗は起きない。と言えます。
細菌の活動条件は5つ
「水分」
「栄養分」
「温度」
この3つが揃うと、腐敗の原因の細菌の活動が活発になります。
栄養分を抜いてしまうと、せっかくの食材のメリットがなくなり、冷蔵庫がない時代に温度を一定に保つのは難しい。
となると「水分」を抜くしかなくなります。
そこで昔の人は、水分を抜くために塩に食材を漬けました。
これが漬物のはじりまりです。
これが副次的に細菌が生きていけない高濃度な塩分が実現されたことで、ダブルで腐敗を防ぐことができ、長期保存の手法として確立していきました。
しかし、最近では健康志向の高まりにより、塩分を気にする消費者にあわせて、塩分濃度の低い漬物が流通するようになりました。
この塩分濃度というところがポイントで、低すぎる塩分では食材の腐敗を防ぐ事ができないんです。
塩漬けで言うと、最低でも20%ぐらいの塩分濃度が必要と言われています。
この塩分濃度が20%以下で作られたお漬物は、お漬物なのに食材が腐敗することが起きて、2年前食品衛生法の改定により、お漬物を作る場合、保健所への届け出が必要になりました。
その様な背景もあり、近年の漬物離れが起きていると言われています。
そんな漬物ですが、日本ではじめて漬けられた食材はなんだと思いますか?
一応、記録として残っているものに限定しています。
大根?
きゅうり?
白菜?
正解は
瓜
だそうです。
瓜として記録されているので、きゅうりかもしれませんし、冬瓜かもしれません。
はたまたカボチャかもしれませんね!
カボチャはないか・・・。
個人の感想ですが、スイカの漬物は意外に美味しいですよ!
さて、いかがでしたか?
そういえば、最近漬物食べていないなと思った方、家でも余った野菜などに多めの塩を振って揉み込むだけで浅漬
味噌にみりんを入れて、その中に野菜を入れた味噌漬け
意外にも簡単に家でも漬物はできますので、一度お試しあれ!
これは余談ですが...
漬物の代名詞でもある「たくあん」
たくあんは、天日干しした大根を塩と麹で漬けた「麹漬け」に分類されるお漬物です。
云わば「大根の麹漬け」ですが、たくあんがたくあんと言われるのは、このたくあんを考えたのが「沢庵和尚(たくあんおしょう)」と言われており、この和尚様が作ったお漬物を徳川幕府三代将軍徳川家光が大変気に入り、「大根の麹漬け」の和尚様の名前から「たくあん」と名付けたと言われています。
この記事はいかがですか?
記事を評価してストーンをGET
他の記事
.png)